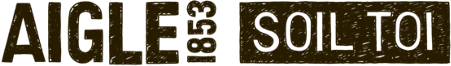
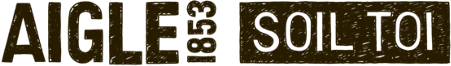
23.05.30

柳田大地
農家
やなぎだ・だいち|1988年、埼玉県生まれ。 アパレル業界で働きながら、埼玉県比企郡小川町にて有機農業を学ぶ。現在は農家 に転身し、小川町に移住。不耕起、無農薬、無肥料で野菜を育てるSOU FARMを運営。青山ファーマーズマーケットへの出店など、移動販売も行う。
Instagram:@sou_farm

まだ有機農業という言葉が一般に浸透していなかった1970年代から、化学肥料や農薬に依存しない農業が行われてきた埼玉県比企郡小川町。今も日本有数の“有機の里” として有機栽培が盛んなこの地に惹かれ、アパレル業から転身した若き農家がいる。それがSOU FARMの主である柳田大地さん。なぜ彼は農家としての生き方を選び、日々土と向き合うのか。その理由を探るために、我々は彼が暮らす小川町を訪ねた。
午前6時。あたりが朝日で赤く染まる早朝から、AIGLEのブーツを相棒にして収穫に励む柳田さんの姿がそこにあった。「AIGLEのブーツは履くたびに足になじむ感覚があるんです」と話す柳田さんがこのとき育てていたのは、のらぼう菜やケール、フェンネルといった野菜たち。すべて不耕起の畑の中で育てられたものだ。“不耕起” について柳田さんに問うと、「不耕起といってもいろんな向き合い方がある」と前置きをした上で、次のように教えてくれた。 「うねを立てた後は耕したりせず、なるべく生き物の営みを尊重しながら野菜たちを仲間入りさせて育てます。耕すというのは野菜を管理しやすい環境を整えるために、人間の都合でその土地をリセットすること。それをせず、そこにいるすべての生き物と関係を築いていくというのが僕の考える不耕起です。
目先の実りのことだけを考えたら肥料を与えるなど、もっと効率のいい方法があることを知っています。でもそれをしない理由は、野菜を育てるためだけに畑をやっているわけではないから。うねの一つひとつがよくなれば畑が、そして畑がよくなれば町全体の環境がよりよくなる。自分にできるその第一歩として、不耕起という方法で目の前に向き合っています。一歩一歩を積み重ねることで本当の意味の持続可能性を生むことができると思っているんです」

最低限の手入れにとどめられたSOU FARMの畑。自生した野草と柳田さんが仲間入りさせた野菜が、ともに不耕起の土壌に共生している。
「野菜を育てるための農業ではない」。そう力強く話す柳田さんだが、その想いは農家として畑に向き合う中で育まれたものであり、農に関心を持ったのは食への興味からだったという。
「母はわざわざ車で30分ほど離れたところにあるデパートに行って有機栽培の野菜を購入したり、みんながおやつにポテトチップスを食べている中、僕には煮干しを出してくれたり。母は彼女自身のためというよりも、常に僕が口にするものに気を遣ってくれる人でした。『なぜそこまでこだわるんだろう、なぜ僕はみんなと同じものを食べられないんだろう』と、不思議に思っていましたが、大人になるにつれて母がそうしてくれた意味を理解できるようになりました。食べるものが自分の体だけではなく心も育んでいるということ、そして食が生きる上でいかに大切なのかが感覚としてわかってきたんです」
そして「10代の前半には農家として自分で食べ物を育む人になりたいと考えていた」と話す彼は、「祖父が大工だったこともあってか、食に限らず生きるために必要なものにはなるべくダイレクトに向き合う生き方をしたいとも思い描いていた」と続ける。彼がキャリアのスタートをアパレルの世界に決めたのもそれが所以。食とともに人の暮らしを支える衣食住のうちの“衣” がどう成り立っているのか、それを掘り下げるための選択だった。
「自分の中で30歳までには農家として独立をしようと決めていたので、当時のデザイナーにもゆくゆくは農家になると伝えた上で面接をしてもらいました。そして自分と衣の関係性を探りながら、農業の勉強ができる場所を探して出会ったのが“有機の里” と呼ばれる小川町でした」
かくして休日に小川町の農家のもとで有機農業を勉強する生活が始まった。「当時まだ浅い知識の中で、自分が実現したいことは自らの枠組の中で叶えられると思っていました。でも実際に飛び込んでみると、本当にあらゆる面で多くの人やものに支えられて生活が成り立っているという現実があった。トラクターや資材だけでなく、多くの農家が種も購入していることを知りました。たとえば今この畑にはのらぼう菜が育っていますが、暖かくなると葉が茂って花を咲かせて種を残してくれて、僕はそれをまた秋に蒔く。そうして育ったのらぼう菜は、もとののらぼう菜と別のものには思えないわけです。もとの株はもう命を終えてしまうかもしれないけれど、残った種を通して僕はまたこの子とつながっている。1年で途切れてしまうのではなくて、植物との関係性を積み重ねていきたい。だから自ら種を採って蒔くというのは自分にとって大事なこと。毎年収穫を終えたら種ができるのを待たずに畑をならし、また種を購入しなければ営みが成立しないという現実に僕は納得がいかなかったんです。もちろん 研修ではポジティブにいろんなことを学んで吸収できたけれど、それと同時に常に自分だったらどうしていきたいのか、この場所で自分が素直に生きるためにはどうすべきなのかを考えた結果、今の不耕起という形になっていきました」

柳田さんの人参はボコッとしていて表情豊か。「その形は人参が必死に生きた証」
彼が自身のスタイルを確立するためのヒントとなったのが、ありのままの自然が発するメッセージだったという。
「自生している草花がうねによって違っていて、『なんでこんなところにこの草が生えてくるんだろう?』と不思議に思ったんですね。でも、それも自分自身に置き換えたらわかること。人間は自分にとって意味のないところで生きな いじゃないですか。それと同じで草花は環境が整わなければ発芽しない、休眠という性質がある。つまり発芽したということは、この草にとっては何か納得できる理由があったということ。そういう一つひとつのことが自然からのメッセージなのだと気づいたときに、野菜をつくるだけじゃなく、この土地全体が豊かになる関わり方をするのが自分のすべきことだと思わされたんです」
しかしながら、土地を豊かにするためには、人間が手を加えるという方法も考えられるだろう。そんな中でも不耕起を徹底するのは、自然の力強さには敵わないからだと彼は話す。
「ここでは人参も育てているのですが、この子たちが育ったのは粘土質な硬い土。普通人参はふかふかとした柔ら かい土で育てるのがセオリーとされていますが、そうでなくても形は不揃いながらもちゃんと育ってくれる。なんでこ んなに硬いところでも根を伸ばしたかというと、それは子孫を残すため。人間が自ら暮らす環境をよりよくしながら 生きているように、人参も生きるために根を生やして自ら土をほぐしていくんです。そしてその土は、耕さなければそ の命の証としてずっと残っていく。それを種が蒔きづらいからとか、土が硬いからといった僕たちの都合でリセットす るのではなく、ほんの少しだけ場所を整えてあげて蓄積させていくことで、徐々にこの子たちが生きやすい場所に変 わっていく。時間はかかるけれど、それが本当の意味で土地が豊かになっていくということだと思います」
柳田さんも話すように、不耕起とはまったく人の手が介在しないことでない。すでにあるものを極力活かしなが ら、朽ちた野菜から種という命のバトンを預かり、また新しい芽を育むために落ち葉を集めて温床をつくる。そしてその熱が、育苗の手助けとなるのだ。「落ち葉は、寒い時期に役目を終えて枯れたものだけれど、それを丸2年外に野積みすると、苗の土になる。そしてその苗土が種に息吹きを与え、種がまた畑に移って野菜として育ち、それをお裾分けしてもらって私たちが食べるわけです。つまり今年拾った落ち葉が、形を変えて2年後の自分自身になるということ。そうやって今がすべて未来とつながっているということを畑は教えてくれるんです」

「不耕起農法や不耕起栽培というと野菜の育て方のように思われがちだけど、耕さないっていうのは土との向き合い方のことなんです」
柳田さんには最近野菜づくりとともに取り組んでいることがあるという。それが土器づくりだ。
「畑に水の通り道をつくる際に溝を掘るのですが、その土を使っています。『土は生命のプロダクト』という言葉が 大好きなのですが、土器をつくると自分の暮らしと土が密接に関わっていることがわかります。土はどこかから飛ん できて積もっているわけじゃなくて、生き物たちの営みがあって、ここに蓄積している。物語があるわけですよね。土は生き物を育んでいくこともできるし、器のように形を変えて暮らしを豊かにすることもできる。そういう『自分たちの暮らしの土台は土である』という価値観を、この場所を通してみんなと分かち合いたい。ただ単に野菜が育てられてよかった、ではなくて、野菜を育てたことが何につながっているのかということが大事。今は農業が食料を生産するための営みになっているところがあるけれど、本来はそうじゃない。お腹を満たすというのはあくまでもおまけみたいなもので、自分たちの暮らしの土台となる場所を守っていくために農業があると僕は思っています。野菜も土もそこで生きる微生物も、ともに作用し合いながら生きていて、もちろん人間も含めすべてが対等な立場。そして、そのすべての生き物の関わり合いによって畑がつくられる。そういう物語を、この小川町という場所でみんなと共有していきたい ですね」
こうやって自分がいる場所への興味を積み重ねることが、人間が直面している環境問題に一石を投じることになっ ていくという。
「僕は環境問題のことも意識して農家の道を選びましたが、地球規模のあまりに大きな課題なので当初は何をしたらいいかわからず、自分事になっていなかった。でも、小川町という大好きな場所をよくしようと思うと、次第に自分事になっていったんです。僕のように、より多くの人に自分にとっての大切な場所を心の中に育んでもらいたい。そしてその場所との関わり方をこの畑を通して持ち帰ってもらう。個々の活動の点が広がれば地球全体につながっていくと思うのです。長い時間はかかるかもしれないけど、みんなそれぞれ自分が関わっている大好きな場所、大好きな土をよりよくしていこうと行動できたら、それは大きな変化を生むはず。そのために単に野菜を育てる体験をしてもらうのではなく、土地をよりよくするために種を蒔き、苗を植えてもらう。ほかにもミツバチを今年から育てようと思っていて、その巣箱をみんなでつくって設置してみたり。ここを自分だけではなく、みんなと一緒によりよくしていくための集いの場にしていきたいと考えています。この畑が変化のためのきっかけとして機能してくれたらうれしいですね」

SOU FARMは妻の彩子さんと運営。この日は2人で収穫。途中見知らぬ野草を見つけて「ハーブティーによさそう」と、味見する場面も。

柳田さん作の土器。畑に水路をつくるために掘った溝の土を使用。土は命を育むだけでなく、器などに形を変えても我々の生活を支える。
サステナブルという言葉を街中いたるところで耳にする現在、環境のために、という思いを持っている人も少なくないだろう。しかしながら、特に都会で暮らす人にとっては、自然と関わり、環境配慮の第一歩を踏み出すというのは ハードルが高いと捉えられることもある。しかし、柳田さんはどこにいても自然に向き合うことができると話す。
「僕が意識しているのは、誰にでもできるということを表現すること。僕も農家になる前は『トラクターを持ってい ないと農業はできない』とか、『知識がないと無理』などと先入観があった。でもそんなことはどうでもよくて、自分と土とほかの生き物の営みについて考え直すだけで、どんな人も自然と向き合うことができます。自然が好きというと、『山に行ってリフレッシュしています』と言う人もいるけれど、たとえ都会にいてもプランターがひとつあればそこに自然をつくることができるんですよね。自分の暮らしと遠いところにしか大自然は存在しないと思いがちだけど、食べるということを通してどこかの環境とつながっている以上、大自然はとても身近なものなんです」
最後に今後の展望を聞いた。
「僕の考えは5年後にはまた変わっているかもしれない。けれど、自分が関わることでこの土地をより豊かにすると いう目的だけは変わりません」