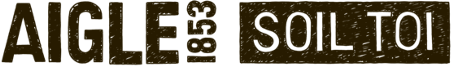
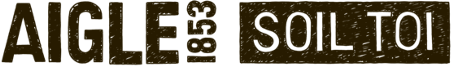

1800年代から今も変わらずフランスを拠点に、農家のための長靴を生産し続けている「AIGLE」が”SOIL=TOI”(土とあなた)という理念のもと、国内の“土”と共に生きる様々なスタイルをもった農家の方々を紹介します。大地と共に生きる、地球人として自然と共生する、そんな大きなテーマを考えるときのヒントやきっかけがそこにはあります。
長野県北部の山間に位置する千曲市倉科に、依田研一さんご夫婦が営む「の音wines」という、人気のワイナリーはある。最近、よく耳にする自社栽培による葡萄をつかったオリジナルの国産ワイナリー、その現場を見てみたくなって冬の長野に車を走らせた。
まだ雪は積もっていない、吹雪いてもいない晴れ間のある12月、車を走らせながら、千曲川の流れる千曲市に入る。そして“杏の里”の看板が立ち並ぶ倉科の街の小高い山の麓に広がる葡萄畑、その葡萄の丘を登った、丘のてっぺんにまだ真新しいワイナリー施設と、古民家を改装して作られた素敵なカフェが並んで顔を出しているのが見えてきた。地域の特性を活かし、地元の文化やコミュニティとの繋がりを大切に、自然と調和したワイン作りを実践している「の音wines」の依田夫妻にここまでの経緯やこれからのこと、いつものような雑談が始まった。笑


-自分でワインを作ろうと思った、その経緯を教えてください
研一さん)
元々自分はソムリエを生業として働いていました。ここ、長野県千曲市で生まれ育ち学生の頃はとにかく都会に行きたくて東京の大学に進学して、賄いが食べられるって理由で飲食業界働き出しました。最初はバーテンダーだったんですけど、その時にお酒のある場の魅力を知って、そのまま大学を卒業してからも飲食レストランサービスの業界に残りました。せっかくやるなら極めたいと思い、ワインの勉強をして都内のレストランでソムリエとして働いていました。そのうちにたまたまご縁があって、沖縄のリゾートホテルの開業の話をいただいて、働く拠点を沖縄に移しました。こんな山に囲まれた場所で育ったので、青い海の近くに住むって夢みたいなお話で。そこで妻に出会って結婚して、子どもも生まれて結局10年ぐらいは沖縄にいましたね。
こんな田舎で育ったもんですから、都会に憧れて地元を出て、東京でワインの仕事をしていたら世界と繋がって、フランスやオーストラリアに足を運んだりして意識が“外に外に”向いていたんです。でも、年々世界のワイン業界でも日本のワインの評判が上がっていったんです。しかも、山梨県はもちろんのこと、北海道や自分の地元の長野県が新しい産地としてクローズアップされてきて、「え、俺の地元じゃん」って。(笑)
妻も沖縄出身ですし、仕事も子育ても、とても充実していましたが、いつか自分が育った故郷で子どもを育てたいなって勝手に思っていて、それとワインを作りたいという気持ちが交差してしまい、「地元に戻ってワインを作りたい」と妻に相談しました。彼女は沖縄で生まれ育ち、地元の会社で仕事もしてましたから、そんな急な話。。
いい迷惑ですよね。(笑)
妻には、もう本当に感謝しかありません。
幸江さん)
私の実家は、沖縄で釣具屋を営んでいて、すごく天気に左右される仕事で、しかも釣りを趣味にする人って一部じゃないですか。そんな不安定な仕事を間近で見ていたので絶対天気に左右される仕事にはつかないし、そんな人とは結婚しないって思っていたんですが、なぜか今農業をやっていて。(笑)
しかも、ワインも嗜好品ですし。(笑)
人生何があるかわからないなって。
ここに来る前は本当に沖縄を出たことなかったので、長野以外は知らないんですが、この場所がいいのは晴れの日が多いこと。全国的にも雨量が少なくて、カラッとした晴天が続くと本当に気持ちが良くて。ここ数年、醸造所や併設しているお店の立ち上げがあったのでずっと帰れてなかったのですが、今度3年ぶりに沖縄に帰省できるのでめちゃくちゃ楽しみです!

-ワイン作りへのこだわりを教えてください
研一さん)
2016年からワイン醸造を実現させるために動き出しました。ワイン作りもヨーロッパだと大きく分けてドメーヌとネゴシアンって2つの形があって、ドメーヌっていうのは、葡萄の栽培から醸造や熟成、瓶詰めまで全て自社でやる。ネゴシアンっていうのは自社畑は持たずに、葡萄農家やドメーヌから葡萄やワインを購入して醸造、熟成などをして瓶詰めして販売する。自分は、性格的にもドメーヌをやりたくて、葡萄栽培の勉強から始めました。
ワインの味を決めるのは8.9割原料の葡萄って言われてる中で、そこを自分でやらないって選択肢はありませんでした。まずは、地元千曲市に畑を借りて、山梨県の先進ワイナリーさんのところで勉強させてもらいながら、そこで譲っていただいた葡萄の苗木を自分の畑に植えて育て始めました。それと並行して、ワインの作りと、ワイナリーの設立や経営などは、山梨県の98winesさんで勉強させてもらいました。
まだ家族は沖縄にいましたし、養っていかないといけないので、その時働いていた沖縄のフレンチレストランで2週間働かせてもらいながら2週間こちらで修行という生活でしたね。あの時は、本当に大変だったのでもう思い出したくないです。(笑)
葡萄栽培としては、化学農薬と化学肥料は使用せずにワイン用の葡萄を育てています。特に、有機や自然派だから良いとかそういった考えではないのですが、初めての消毒は教科書通りのやり方で化学農薬も使ってみたんです。ただ、殺虫剤を使うとあれだけ虫の声がしていた畑がシーンと静まり返って畑が生きてる感じがしないし、妻やパートさんに、除草剤も含めた化学農薬を散布した畑で作業してもらうのも自分の中で何か引っかかってしまって。
作業量は増えるんですが、なるべく使わないやり方のバランスを試行錯誤してこの形になりました。この規模感だからできるっていうのもありますけどね。ただ、全ての葡萄を自社畑で賄えないので、有機栽培ではない近隣の農家さんの葡萄を買わせていただくこともあるので、特にそこを強く打ち出そうとは思っていません。ワイン作りの部分での、亜硫酸塩(酸化防止剤)を使わない製造は研修先の98winesさんでみっちり教わったので、生々しいネイキッドな味わいは表現できてると思います。ただこれは、とてもハイリスクな製造方法なので日々葛藤してますし、悶々ともしちゃいます。それでも自分がやっぱりソムリエとしてずっとやってきたので、何よりも“からだと心にやさしくて、美味しい”っていうことを大事にしています。
2018年~2022年は醸造所さんに委託という形で、間借りをしてワインを作らせていただいていました。原料の葡萄が収穫できるのも、苗木を植えてから5年は必要ですので、家族やパートさんの力も借りながら栽培も進めて。そして、2023年にこの醸造所を建てて、自分たちで栽培した葡萄を使い、自分たちだけで作ったワインが完成しました。「の音wines」ファーストビンテージは2023年。2016年からの苦労がやっと形になりました。




-これからの夢とかやりたいこととかありますか?
研一さん)
ワインってその土地のお酒だから、自分のワイナリーの名前は、産地にゆかりがある言葉を付けたかったんです。でも、千曲や倉科をそのままつけることは何かピンとこなくて。
ある時、フランスの友人がふと「千曲市って1000の曲って書くんだね」って話をして、その時バラバラだったパズルが1つにまとまった感じがして。曲を奏でるようにワインを作って、今年の1曲、来年も1曲って毎年曲を作っていって、いつか1000曲になったら良いよねって。それに、この山に囲まれた畑にいると、自分の作業の音だけじゃなくて、鳥や虫、風、一緒に働く人たちの音がしてそれも曲の一部ですし、ワインが出来上がる工程の中で、自然や家族、友人、取引先の方々などのみんなの繋がりが響き合ってワインという曲ができる。そんな“ワインの音”ってイメージで「の音wines」と名付けました。
この辺りってワイン作りの特別良い産地じゃないんです。もっと適したところは日本にたくさんあるんですが、やっぱり自分の中では“地元でやる”ってことに価値があって。
そこからどう表現して、どう世界と繋がっていくかってことを考えてきました。
やっと、スタートラインに立てたところなので、まだまだ道の途中ですが、このワイナリーがひとつのハブになって、もっと人が集まって、そして、千曲が倉科が活性化していったらいいなと思っています。僕がこの場所にワインの音を置くことで、今回AIGLEさんが取材に来てくださったこともそうです。実は、僕のワイナリーが出来たことで、畑の隣でパン屋さんやろうって友達が言っていて、そうやって、別の知人がコーヒーショップやろうかな、ゲストハウスやるよって、っていうふうに、どんどんその輪が広がっていけばいいなって思っています。そして、いつかそれが集まって毎年異なる曲が生まれて、それが10曲、100曲、1000曲になっていったらいいなって。もしかしたら、元々そういう意味で先人の方が付けた地名なのかなとも思うので、次は僕たちが現代の形で循環させる番ですね。


-最近、僕のアンテナに引っかかってくるのは、都心でなく、地方での地域に根差したおもしろいコミュニティの話や、その人たちがさらなる共鳴を読んで、また新たな文化や循環可能なビジネスを生み出しているという話です。
現代日本の都市部における、消費社会、経済成長を真ん中にした街には、文化が残っていくんだろうか?何を規範に生活し、理想として社会をつくればいいのか?手探りを続ける僕たちに、労働って楽しいもんでしょ!ってことや、目的が同じ人が集まると、それで仲間っしょ!ってことだったり、当たり前のことを再認識、いや思い出させてくれる。
-追記しておきたいのは、取材中に頂いた、幸江さん手作りのバスクチーズケーキは、本当においしくって、この場所で収穫され、発酵したワインにも合います。
「の音wines」を訪れた際には、是非ワインや葡萄ジュースと併せて、食べて頂きたいです。

の音wines
写真・取材記事 : SHOGO
モデル業の傍ら、自身でも農地を借り、時間が許す限り、 作物を育て、収穫し、食す。農家見習い兼モデル。
IG https://www.instagram.com/shogo_velbed/