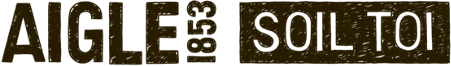
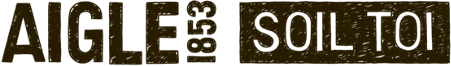

1800年代から今も変わらずフランスを拠点に、農家のための長靴を生産し続けている「AIGLE」が”SOIL=TOI”(土とあなた)という理念のもと、国内の“土”と共に生きる様々なスタイルをもった農家の方々を紹介します。大地と共に生きる、地球人として自然と共生する、そんな大きなテーマを考えるときのヒントやきっかけがそこにはあります。
長野駅から車で30分ほど走ったところにある善光寺平の北部に位置する豊野町。四方を2〜3000m級のアルプスなどの山々に囲まれた盆地では、葡萄や栗、そして林檎の栽培が盛んな地域だ。12月のカラッとした晴れの日に、思わず車窓を開けて、圧倒的な大きさで眼前に迫ってくる北アルプスを横目にみながら車を走らせると、あたり一帯が、真っ赤な実をつけたリンゴの木々が立ち並ぶ、広大な農園地帯に突入した。ラジオの音と忙しなく作業をする農家の方々の元気な声が一帯で聞こえてくる。そう、今は林檎収穫の最盛期の最後の時期だ。今回取材を受けてくださった「宮下果樹園」の宮下直也さんは、120年続く林檎農家の5代目。AIGLEの取材で、ひとつの作物を先祖代々で継承している農家さんを取材するのは今回が初めてだ。豊かな自然環境に恵まれ、信州りんごの名産地として知られている豊野町で、「シナノスイート」や「シナノゴールド」などの高品質なリンゴを栽培し、新たに手作りのジャムやシードルなどの加工品の展開へも挑戦し、林檎の魅力を発信している宮下さん。果樹農家という家業を継承するということ、そして新たな形で未来へ繋いでいくということ、林檎とそこに込めた思いについて話を聞いてきた。


-林檎農家を継承しようと思ったきっかけと経緯を教えてください
宮下さん)
畑の手伝いは3歳からやってました。しかも、僕が宮下家の60年ぶりの男の子だったので、生まれて1秒で農家になっちゃった。ライオンキングのシンバを抱える感じだったみたいです。跡取りだー!って。(笑) ある意味英才教育なんですが、そのプレッシャーを0歳の時から受けて育ったので、案の定、思春期の時に「ここを飛び出して違う世界も見たい!」という思いが強くなりました。ちょうどその頃、日本のファッションシーンや裏原カルチャーが盛り上がっていた時で、高校の進路希望調査書にモード学園やバンタンデザインなどのファッションが学べる東京の専門学校を書いて親に渡したら、母親にいきなりビリビリっと破られまして。「何言ってんの!バカモノー!」って。(笑)そこからは、どうやったらこの場所を抜けて都会に行けるのかを考えだして、ある時閃いたんです。「そうだ!大学で農学部に行けば、親にも反対されずここを一旦離れられるんじゃないか。」って。東京じゃないけど、大阪もアメ村とか若者のファッションが盛り上がっていることは知っていたので、これだ!と思って、近畿大学の農学部に進学しました。これで晴れて、都会の生活を思いっきり楽しめると思ったら、近畿大学の本学部は大阪府の中心部にあるんですけど、農学部は奈良県の陸の孤島のような里山にあって、「えっ、地元よりも田舎じゃん。。」って。(笑)そこからまた田舎での四年間がスタートしました。その後、卒業して就職の時は親もまだ元気でしたし、そこまで反対も無く、大阪で株式会社アダストリアに就職して念願の都会ライフが始まりました。
都会での生活はとても楽しく充実したものでした。でも、そのうち不思議とだんだん登山やキャンプなどの自然遊びに惹かれていって、ある時この辺りの山を登りに来た時に、「あれ、こんなに俺の地元って素敵なところだったんだ。」って気付かされて。その時くらいから少しずつ将来的に自然に関わる仕事をしたいと思い始め、色々考えていたらある時閃いたんです。「家業あるじゃん!」って。(笑) そんな時に、母親が体調を崩したんです。実家から野菜とかお菓子とかよく仕送りを送ってきてくれたんですが、そこに母親から一通の手紙が入っていて、「帰って来て家業を継いでくれないか。」って書いてあったんです。そんな実家の状況と、自分の将来の仕事への気持ちが合致して帰ることを決断しました。その時大阪で出会った奥さんと結婚していたので、一緒に長野に移住して家業を継ぐことになりました。その時が28歳で、今37歳なので9年前の話ですね。


-林檎を育てるときにこだわっていること、大切にしていることを教えてください
宮下さん)
この土地は、とにかく晴れが多く雨が少ない土地で。囲まれてる山々のアルプスとか嬬恋とかの県境の方で降って、こちらの盆地では雨が少ないんです。なので、畑にはそこの千曲川からポンプで水を汲み上げてスプリンクラーで撒いてます。この辺りがリンゴの産地になった背景としては、現在、表参道にある青山学院大学のキャンパスのところが、昔は農業試験場だったみたいなんですが、そこに1905年にアメリカからリンゴの栽培技術が入ってきて、これを全国で育てて日本の名産にするぞって盛り上がっていた時で、そのタイミングで長野の農家さんたちも始めたみたいです。寒暖差があって、雨が降らない土地がリンゴの栽培に適していたみたいで、信州ではこの豊野町や赤沼辺りがリンゴ栽培の発祥の地みたいです。
そういった意味で、父親という絶対的な師匠であり、林檎の歴史の教科書がそばにいるっていうのは、大きいですね。父親とは、先祖代々受け継がれてきたことと、時代に合わせて変えていかなければいけないことのバランスを毎日のように話し合いながらやっています。時にはもめながら。(笑)
でもやっぱり親父が培ってきた経験はすごくて、収穫したリンゴを出来によって13種類に仕分けしていくんですが、その目利きもめちゃくちゃ早いですし、剪定の見極めにしても学ぶことばかりで。リンゴって本当に奥が深すぎて色々な農法があるんですけど、最近だと、アメリカやオーストラリアで流行ったわざと細長く縦に伸ばして収穫量を上げて作業性を効率化させる”高密植栽培”と言うやり方が日本でも広がって来ていて、うちも実験的に採用している畑もあるんですが、やはりメインはよく絵本とかで描かれているような、どっしりと太い幹で枝や葉が横に生い茂っている、古くから受け継がれている方法で栽培しています。それがとてもシンプルなんですが、ゆえに奥深いんです。木の力を栽培技術でどれだけ引き出して、葉の光合成を最大化させるかっていうとてもシンプルな戦いで。
うちは太陽・土・根・葉を最大限活かした栽培を重視しています。細かい技術は置いといて、その4拍子が揃った時のコクやウマミははんぱなくて、植物の力って本当にすごいです。また市場より2週間ほど遅くギリギリまで樹上で完熟をしてから収穫しているので、一度食べたら病みつきになる長野のりんごの美味しさを最高の状態を味わってもらいたい!というこわだりを持ってやってます。


リンゴの木って全然大きくならなくて、リンゴ農家では子どもが産まれたらリンゴの木を一本植えろ、って言われるくらい育つのに時間がかかる。10歳の木でもまだ若くて、遊ぶぞ―!みたいな感じで枝を伸ばしたり体を大きくすることに夢中で全然実がならない。20歳くらいでやっと「私そろそろ子ども欲しいわ」みたいな感じで実を付けてくる。天真爛漫だった少女がいつの間にかレディーになって、すごく母性に溢れた子煩悩なママになるみたいなイメージです。(笑) その見極めがとても大切で、収穫が終わってからの1~3月に木の年齢や生育の様子を見ながら剪定して整えていくのですが、そこが勝負の時期で。収穫が終わってやっと遊べる!と思っても、一息つくとすぐに始まるので、うかうかスノボや登山に行ってられません。目の前に雪山遊びの最高なフィールドは広がってるのに。。(笑)
現在、宮下果樹園では30種くらいのリンゴの品種を約3ヘクタールの土地で育てていて、最近ではその合間の時期に葡萄栽培も始めました。2019年の台風19号の時に千曲川が氾濫して、ここ一帯の平野部全部木がすっぽり浸かっちゃって。ちょうど実がなってそろそろ収穫って時に全部ダメになっちゃったし、畑も泥やゴミでぐちゃぐちゃだったので、もう農業続けられないかもって本気で思いました。そんな時に娘が生まれて、親や先代の方々が僕の代までこの畑を繋いで来てくれたのに、自分は子どもに何も残せないかもって本当に落ち込み、心が折れそうになりました。ダメになってしまった林檎畑に、収穫までの期間が林檎よりも短い葡萄の木を植えました。娘の名前がニナって言うんですが、葡萄の品種でクイニーナっていうのがあって、いつか大きくなった時に娘が自分の名前の葡萄を収穫できたら楽しいよねって思ってクイニーナの苗を植えました。そこから5年経って最近ようやく収穫できるようになりました。
この辺りの農家さんって100年、120年続いているところばかりなので、あまり特別に思ってなかったんですけど、イベント出店とかでお客様や他の農家さんに創業120年ですって言うとかなり驚かれて、改めて120年代々続いていることの歴史を感じるというか。畑に60歳の木とかがそこら中にある感じなので、時間軸が他の農業と少し違うかもしれませんね。なので、“繋いでいく”ってことの重圧と喜びは、いつも強く感じています。

-これからの「宮下果樹園」について目標とかってありますか?
今、うちの親世代の70、80代が超現役世代で。会合とか行くと一人だけ30代で農家の高齢化を肌で感じます。みなさん元気ですごいなって思うんですが、5年後、10年後を思うと技術も含めて継承者がいないと本気でヤバいなって。
少しでも、農家が魅力的に見えたり、農家の可能性を探ったり、やりがいを感じられるような活動は自分の役割の1つだと感じてます。スーパーに並んでいる野菜も、背景には1点1点必ず農家さんがいて、地域の歴史、伝統、文化や作り手のストーリーが絶対あるからそこは本当に伝えたいなって。販売ルートも1つの農家単体だと輸送費を含めて大変なので、地域の農家でユニットを組んで協力し合ったり、農家やフルーツの価値を上げられるように都内の飲食店さんと組んでフルーツアドバイザーという立場で農家さんとの間に入らせてもらったりもしています。飲食店さんとの取引だと、基本は買い叩かれてしまうので、そこをしっかり農家さんの想いやストーリーをシェフに知っていただいて適正価格で買ってもらい、お客様もその背景込みで食事を楽しんでいただく好循環を作りたいなと思って。農家さんって素晴らしい作物を育ててるのに口下手の方が多くて中々想いが伝わらないことがあるんです。自分も農家なので大変さもわかるし、地域のこともわかるから、間に入って農家さんのストーリーを噛み砕いて飲食店さんやお客様に伝えるっていうのをやっていて。最近だと、表参道のレストランに全国の約50農家さんを繋いで、希少フルーツコースっていうのを作っていただいたり、お店の上がアートギャラリーでアーティストさんの展示の際にデザートを出していただいて、農家やフルーツの価値が少しでも上がったら良いなと思っています。逆に農家さんとお店に食べに行って、イチジクとサワラとか、梨とタコとかびっくりするような組み合わせのメニューを、素晴らしく美味しく作っていただいていることを農家さんも知って、モチベーションも上がり、お互いにとって良い関係が築けていけたら良いなと思っています。
母が、リンゴを1件1件送るときに絶対に手紙を一通入れていたみたいで、その手紙が山積みに家にあるんですが、自分たちが被災した時に、その方達が心配して電話やFAXが鳴り止まないくらい連絡をいただいて。母が築いてきたその信頼関係に本当に感動しました。復興作業の際も、たくさんのボランティアさんが来てくださって、その中に農家さんもたくさん助けに来てくれて。そんな皆さんのおかげで宮下果樹園を繋いでいくことができたので、その恩返しをしたいという思いは強いです。都市と田舎の両方見てきた自分だからできる役割を全力で全うしていきたいと思っています。



-今回、林檎収穫最盛期の一年で一番多忙な12月にお邪魔したにも関わらず、直也さんやお父さん、スタッフの皆さんも快く取材に協力してくださいました。みんな湿気のないカラッとしたこの長野の気候のような方々だった。畑に真摯に向き合いながら、リンゴジャムやリンゴのお酒ハードササイダー、ドライフルーツなどの加工品事業、飲食店さんへのアドバイザーや音楽フェスへの出店、槍ヶ岳の山小屋への配送など、直也さんが何人かいるのではないかと思うような多岐に渡る活動の裏には、ただの継承だけではない、農家の価値を上げるという、次の世代としての果たすべき役割と意義があった。東京に戻り、スーパーに向かうと昨日まで高いと思っていた250円のリンゴが安く感じ3つカゴに入れた。直也さんがおっしゃっていた「スーパーに並ぶものにも作り手のストーリー(思い)が絶対にある」という一見当たり前の言葉が妙に身に染みて、いつもより何倍もリンゴが美味しく感じた。

宮下果樹園
写真・取材記事 : SHOGO
モデル業の傍ら、自身でも農地を借り、時間が許す限り、 作物を育て、収穫し、食す。農家見習い兼モデル。
IG https://www.instagram.com/shogo_velbed/